住まいの空気とVOC対策

不動産の疑問
先生、「不動産」と「建築」の分野で『VOC』っていう言葉が出てきたんですけど、どういう意味ですか?

不動産アドバイザー
いい質問だね。『VOC』は、『揮発性有機化合物』の略で、空気の中に気体として広がる有機化合物のことを指すんだ。塗料や接着剤、洗浄剤などに使われているんだけど、100種類以上もあるんだよ。

不動産の疑問
100種類以上もあるんですか!そんなにたくさんあると、どんなものか想像しにくいです…。具体的にどんな影響があるんですか?

不動産アドバイザー
VOCは、大気汚染や、いわゆるシックハウス症候群の原因物質なんだ。だから、建築材料を選ぶときには、VOCの少ないものを選ぶことが大切なんだよ。法律でも排出量を規制しているくらいなんだ。
VOCとは。
「ふどうさん」と「けんちく」にかかわる「きせいか ゆうき かごうぶつ」についてです。これは、空気中にふくまれる、蒸発しやすい有機化合物のことで、英語の「Volatile Organic Compounds」を略して「VOC」とよばれています。空気の汚れや、シックハウス症候群の原因となるもので、たとえば、ベンゼン、トルエン、キシレン、酢酸エチル、メタノール、ジクロロメタンなどがこれにあたります。このような物質は100種類以上もあり、塗料や接着剤、洗剤などに使われています。空気の汚れを防ぐための法律では、ある程度の大きさ以上の建物などを「きせいか ゆうき かごうぶつ はいしゅつ しせつ」として、いろいろな規制をしています。
揮発性有機化合物とは

揮発性有機化合物とは、常温で容易に気体となる有機化合物の総称です。私たちの暮らしの中で広く使われている、塗料や接着剤、洗浄剤、家具、建材など、様々な物に含まれています。
これらの揮発性有機化合物は、数百種類にも及ぶ多種多様な物質で構成されています。代表的なものとしては、トルエン、キシレン、ホルムアルデヒドなどが挙げられます。
揮発性有機化合物は、大気汚染や健康被害の原因となることが懸念されています。屋外では、太陽光線と反応して光化学スモッグを引き起こし、大気を汚染します。光化学スモッグは、視界不良を引き起こすだけでなく、呼吸器系の疾患を悪化させる可能性もあります。
一方、屋内では、シックハウス症候群の原因物質となることが知られています。シックハウス症候群は、目がちかちかしたり、鼻水やくしゃみが出たり、のどが痛くなったり、頭痛やめまい、吐き気などを引き起こします。これらの症状は、揮発性有機化合物の濃度が高いほど強く現れる傾向があります。
特に、新築やリフォーム直後の住宅は、建材や家具などから揮発性有機化合物が多く放出されるため、注意が必要です。住宅を建てる際には、揮発性有機化合物の放出量が少ない建材を選ぶ、家具は設置前に風通しの良い場所でしばらく保管する、完成後も定期的に換気を行うなど、揮発性有機化合物の濃度を低減するための対策を講じることが大切です。また、家具を選ぶ際にも、揮発性有機化合物の放出量が少ない製品を選ぶように心がけることが重要です。日頃から換気を心がけ、空気清浄機を利用するなど、室内環境を整えることも有効な手段です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定義 | 常温で容易に気体となる有機化合物の総称 |
| 発生源 | 塗料、接着剤、洗浄剤、家具、建材など |
| 種類 | トルエン、キシレン、ホルムアルデヒドなど数百種類 |
| 屋外の影響 | 太陽光と反応し光化学スモッグ発生、大気汚染、視界不良、呼吸器系疾患悪化 |
| 屋内の影響 | シックハウス症候群の原因物質:目のかゆみ、鼻水、くしゃみ、喉の痛み、頭痛、めまい、吐き気など |
| 特に注意が必要な場面 | 新築・リフォーム直後の住宅 |
| 対策 | 揮発性有機化合物の放出量が少ない建材・家具を選ぶ、家具設置前に風通しの良い場所で保管、定期的な換気、空気清浄機の利用 |
シックハウス症候群への影響
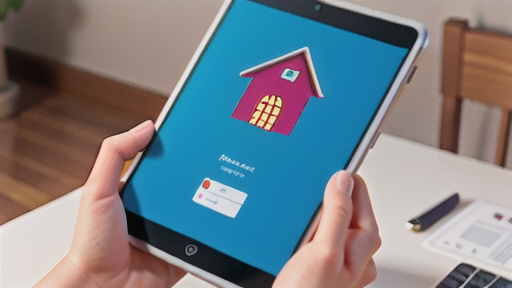
家の建築や改修で使われる建材や家具などに含まれる、揮発性有機化合物といった化学物質が原因で起こる健康被害のことを、シックハウス症候群と言います。 新築や改修した直後の住宅で症状が出やすいのは、これらの化学物質が大量に放出されるためです。
シックハウス症候群の症状は様々です。目がしみたり、鼻水やくしゃみが出たり、のどが痛くなったりする方もいます。その他にも、頭痛やめまい、吐き気などを訴える方もいます。これらの症状は、化学物質の濃度や、その人それぞれの体質によって、現れ方が違います。軽い場合は数日で良くなることもありますが、症状が重い場合は、長引く場合もありますので注意が必要です。
シックハウス症候群を予防するためには、化学物質の発生源を減らすことが大切です。家具を選ぶ際には、化学物質の放出が少ない材料を使ったものを選びましょう。また、建築や改修を行う際には、なるべく化学物質の少ない建材を使うことを心がけましょう。
最も重要な予防策は、十分な換気を行うことです。窓を開けて外の空気を入れることで、室内の化学物質の濃度を下げることができます。特に、新築や改修直後は、より念入りに換気を行うようにしましょう。24時間換気システムを設置することも効果的です。
シックハウス症候群は、適切な対策をとることで予防できます。快適で健康的な住まいを作るために、これらの点に注意しましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| シックハウス症候群とは | 建材や家具などに含まれる揮発性有機化合物といった化学物質が原因で起こる健康被害。新築や改修直後の住宅で症状が出やすい。 |
| 症状 | 目のかゆみ、鼻水、くしゃみ、喉の痛み、頭痛、めまい、吐き気など。症状は化学物質の濃度や個人差によって異なる。 |
| 予防策 |
|
VOC排出規制の現状

揮発性有機化合物(ブイオーシー)による大気の汚れや、私たちの健康への悪影響を防ぐため、国は様々な対策を進めています。工場や事業所などから出るブイオーシーの量を制限する法律が作られ、排出量の基準はより厳しくなり、排出を抑える技術の導入も進んでいます。
具体的には、工場の煙突などに設置する排気浄化装置の性能向上や、ブイオーシーの発生が少ない原料への切り替えなどが挙げられます。また、定期的な点検や測定を行い、排出量を常に監視することで、基準超過を防ぐ取り組みも重要です。
建築の分野でも、建材や塗料などに含まれるブイオーシーの量を制限する決まりができました。家やビルを建てる際に使う材料を選ぶときには、ブイオーシーの少ない塗料や接着剤を選ぶことが推奨されています。環境への負担が少ない建材を使うことも増えています。例えば、ホルムアルデヒドなどの有害物質の放出量が少ない木材や、再生材料を使った建材などが利用されています。
これらの決まりや取り組みのおかげで、ブイオーシーの排出量は少しずつ減ってきています。しかし、大気をきれいにし、健康を守るためには、更なる対策が必要です。例えば、ブイオーシーを発生させない新しい技術の開発や、私たち一人ひとりが日常生活で使う製品を選ぶ際に、ブイオーシーの少ないものを選ぶ意識を持つことなどが大切です。より良い環境を未来に残すため、国、企業、そして私たち皆で協力して、ブイオーシー排出量の削減に取り組んでいく必要があるでしょう。
| 対策の対象 | 具体的な対策 | 追加説明 |
|---|---|---|
| 工場・事業所 | 排出量の制限、排出を抑える技術の導入(排気浄化装置の性能向上、VOC発生が少ない原料への切り替え)、定期的な点検と測定 | 法律による規制強化 |
| 建築 | 建材や塗料に含まれるVOC量の制限、VOCが少ない塗料や接着剤の推奨、環境負担が少ない建材の使用 | ホルムアルデヒドなどの有害物質放出が少ない木材、再生材料の利用 |
| 更なる対策 | VOCを発生させない新しい技術の開発、日常生活でVOCが少ない製品を選ぶ | 国、企業、個人の協力が必要 |
住宅におけるVOC対策

家は、家族が毎日を過ごす大切な場所です。だからこそ、家の空気の質にはこだわりたいものです。空気中に漂う目に見えない物質、揮発性有機化合物(VOC)は、シックハウス症候群などの健康問題を引き起こす可能性があるため、注意が必要です。
家の中のVOC対策で、最も手軽で効果的なのは、換気です。窓を開け、外の新鮮な空気を取り入れることで、VOCの濃度を下げることができます。新築やリフォーム直後は、建材や塗料などからVOCが特に多く発生するため、よりこまめな換気が重要です。具体的には、朝晩だけでなく、日中も数回、窓を全開にして、空気の入れ替えを行いましょう。
また、家具や建材を選ぶ際にも、VOC対策を意識することが大切です。VOCの発生が少ない、自然素材を使った製品や、低VOCの塗料・接着剤を使用したものなどを選びましょう。購入前には、製品のVOCに関する情報を確認することをお勧めします。
室内の緑化も、VOC対策の一つとして有効です。一部の観葉植物には、空気中のVOCを吸収する能力があると言われています。リビングや寝室などに観葉植物を置くことで、VOCの低減だけでなく、リラックス効果も期待できます。ただし、観葉植物によるVOCの吸収効果は限定的です。換気などの他の対策と組み合わせて行うことが重要です。
快適で健康的な住まいを実現するためには、VOC対策を日常的に心がけ、家族みんなが安心して暮らせる環境を作りましょう。
| 対策 | 詳細 | 補足 |
|---|---|---|
| 換気 | 窓を開け、外の新鮮な空気を取り入れることで、VOCの濃度を下げる。 | 新築やリフォーム直後は特に重要。朝晩だけでなく、日中も数回、窓を全開にして空気の入れ替えを行う。 |
| 家具や建材の選定 | VOCの発生が少ない自然素材を使った製品や、低VOCの塗料・接着剤を使用したものなどを選ぶ。 | 購入前には、製品のVOCに関する情報を確認する。 |
| 室内の緑化 | 空気中のVOCを吸収する能力がある観葉植物を置く。 | VOCの吸収効果は限定的。換気などの他の対策と組み合わせて行う。リラックス効果も期待できる。 |
今後のVOC対策の展望

大気汚染や健康被害を防ぐためには、揮発性有機化合物(VOC)への対策は、これからも欠かせない取り組みです。VOC対策は、技術革新、測定技術の向上、人々の意識改革という三つの柱で、今後さらに発展していくと考えられます。
まず、技術革新の面では、VOCの発生を抑える新しい材料や技術の開発が期待されます。建材や塗料、接着剤などに含まれるVOCを減らすことで、発生源からVOCの排出量を大幅に削減できます。また、工場や事業所から排出されるVOCを効率よく回収・処理する技術の開発も重要です。これにより、大気中へのVOC放出を最小限に抑えることができます。
次に、VOCの測定技術の向上も重要な要素です。より精密にVOCの濃度を測ることができれば、より効果的な対策を立てることができます。例えば、センサー技術の進歩により、リアルタイムでVOC濃度を監視できるようになれば、迅速な対応が可能になります。また、小型で持ち運び可能な測定器の開発によって、様々な場所で手軽に測定できるようになり、実態把握の精度向上に繋がります。
最後に、人々のVOCに対する意識向上も大切です。VOCに関する正しい知識を広く普及させることで、VOC排出量削減への協力を促すことができます。例えば、家庭では、VOCを多く含む製品の使用を控えたり、換気をこまめに行うなど、一人ひとりができることから始めることが重要です。また、VOC排出量の少ない製品を選ぶ際に役立つ、分かりやすい表示方法の導入も効果的です。行政、企業、そして私たち一人ひとりが協力して取り組むことで、より良いVOC対策を実現し、より健康で安全な暮らしを築くことができるでしょう。

