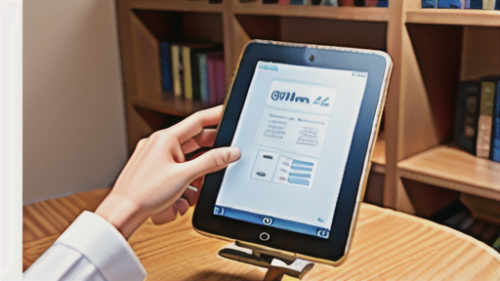家の内装
家の内装 廻縁:美しい内装の秘訣
天井と壁が出会う場所に設置する、細長い部材のことを廻縁(まわりぶち)と言います。見切り縁や天井廻り縁とも呼ばれ、部屋全体の印象を大きく左右する大切な役割を担っています。
一般的に、天井と壁は異なる素材で施工されます。そのため、どうしても接続部分に僅かな隙間や段差が出来てしまいます。廻縁は、この隙間や段差を覆い隠すことで、天井と壁の継ぎ目を滑らかに繋ぎ、美しい仕上がりを実現するのです。
廻縁の役割は、単に隙間を隠すだけではありません。例えば、白い壁と白い天井の間に、木目調の廻縁を取り付けることで、空間に程よいアクセントを加えることができます。また、天井と壁の色に合わせた廻縁を選べば、空間全体に統一感が出て、すっきりとした印象になります。このように、廻縁は部屋全体の雰囲気を引き締め、空間の意匠性を高める効果も持っています。
廻縁には、木材や石膏、樹脂など、様々な素材のものがあります。木材は自然な風合いがあり、温かみのある空間を演出するのに適しています。石膏は加工がしやすく、様々な形状の廻縁を作ることができます。樹脂は軽量で耐久性が高く、水回りにも使用できます。このように、素材によって見た目や機能性が異なるため、部屋の用途や雰囲気に合わせて適切な廻縁を選ぶことが重要です。
廻縁を設置することで、天井と壁の継ぎ目が美しくなり、部屋全体の完成度が格段に向上します。また、廻縁のデザインや素材によって、様々な雰囲気を演出することも可能です。新築やリフォームの際には、廻縁にもこだわって、理想の空間を作り上げてみてはいかがでしょうか。