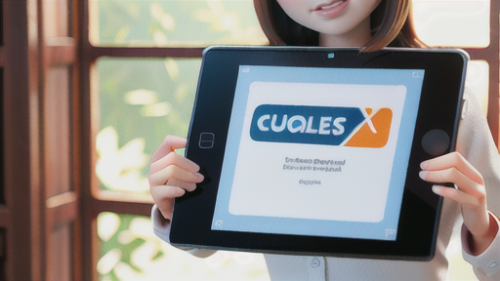防犯・防災
防犯・防災 安心安全な暮らし:24時間セキュリティマンション
人の暮らしを守る上で欠かせないのが安全です。特に集合住宅では、多くの住人が暮らすため、より強固な安全対策が求められます。24時間体制で人の安全を見守る仕組みを持つマンションでは、様々な工夫が凝らされています。
まず、建物の内外には、隅々まで見渡せる監視用の機械が設置されています。これにより、敷地内全体を常に監視し、不審な動きがあればすぐに察知することができます。また、各部屋の玄関には、侵入者を感知する機械が設置されており、もしもの時も安心です。さらに、建物内には、住人以外の人が入らないように、入退室を管理する仕組みがあります。住人だけが持つ特別な鍵や暗証番号によって、部外者の侵入を防ぎます。
これらの仕組みは、一年中いつでも休むことなく稼働しています。例えば、監視機械が不審な人物を捉えた場合は、警備を行う会社へ自動的に連絡が入り、すぐに対応してくれます。また、火災が発生した場合は、火災を知らせる機械と連動して警報が鳴り響き、消防署へ連絡が入ります。同時に、火を消すための装置も作動します。火災の早期発見と鎮火により、被害を最小限に抑えることができます。
このように、24時間体制で安全を守るマンションは、住人の安全を第一に考えた様々な仕組みを備えています。防犯対策はもちろんのこと、災害発生時の対応も万全です。これにより、住人は安心して日々の暮らしを送ることができます。まるで大きな傘の下で守られているような、そんな安心感を提供してくれるのです。