貸家建付地とは?その概要とメリット・デメリット

不動産の疑問
先生、『貸家建付地』ってどういう意味ですか?

不動産アドバイザー
簡単に言うと、自分が持っている土地にアパートやマンションを建てて、人に貸している時のその土地のことを指します。例えば、アパート経営をしている人が持っている土地ですね。

不動産の疑問
なるほど。自分の家に住むための土地とは違うんですね?

不動産アドバイザー
その通り!自分の家に住むための土地は『自用地』と言います。それから、土地を人に貸して、そこに家を建ててもらう場合は『貸宅地』と言います。用途によって呼び方が変わるんですね。
貸家建付地とは。
『貸家建付地』とは、アパートやマンションのように、自分が持っている土地に賃貸住宅を建てて、他の人に貸している土地のことです。たとえば、自分が土地を持っていて、そこにアパートを建てて人に貸している場合は、その土地は貸家建付地にあたります。
一方、自分が持っている土地に自分の家を建てる場合は、その土地は『自用地』と呼ばれます。また、自分が持っている土地を、他の人が家を建てるために貸している場合は、その土地は『貸宅地』と呼ばれます。つまり、同じ土地でも、その用途によって貸家建付地、自用地、貸宅地と呼び方が変わるのです。
貸家建付地の定義

{貸家建付地とは、土地の上に賃貸を目的とした建物が建てられており、それを第三者に貸し出している土地のことを言います。}簡単に言うと、アパートやマンション、借家などが建っている土地全体が貸家建付地に該当します。これらの建物は、所有者が自ら居住するためではなく、家賃収入を得る目的で建てられています。
貸家建付地を持つ主なメリットは、安定した家賃収入を得られることです。毎月決まった収入が入ってくるため、長期的な資産運用として有効な手段となります。また、相続が発生した際には、更地の評価額よりも低い評価額となる場合があり、相続税対策としても活用されます。建物が存在することで、土地の利用価値が限定されるとみなされ、評価額が下がるためです。
しかし、貸家建付地を持つということは、所有者としての責任も伴います。建物の老朽化に伴う修繕や、設備の維持管理、入居者からのクレーム対応など、様々な業務が発生します。建物の管理を適切に行わなければ、入居者の確保が難しくなり、空室期間が長引く可能性があります。空室が増えれば、当然家賃収入は減少します。これは空室リスクと呼ばれます。また、入居者が家賃を滞納するリスクも存在します。家賃滞納が発生した場合、督促や法的措置など、対応に時間と労力を要することがあります。これらのリスクを十分に理解し、適切な対策を講じる必要があります。
さらに、地震や火災などの災害発生時には、建物の損害だけでなく、入居者の安全確保という大きな責任も負うことになります。日頃から防災対策を講じ、入居者への周知徹底を図るなど、万が一の事態に備える必要があります。このように、貸家建付地は安定した収入源となる一方で、所有者としての責任とリスクも伴うことを理解した上で、運用していく必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定義 | 賃貸を目的とした建物が建てられており、それを第三者に貸し出している土地。アパート、マンション、借家などが建っている土地全体。 |
| メリット | 安定した家賃収入、相続時評価額の軽減 |
| デメリット・リスク | 建物の老朽化に伴う修繕、設備の維持管理、入居者からのクレーム対応、空室リスク、家賃滞納リスク、災害発生時の責任 |
| 所有者責任 | 建物の維持管理、入居者対応、災害対策など |
貸家建付地と他の土地との違い
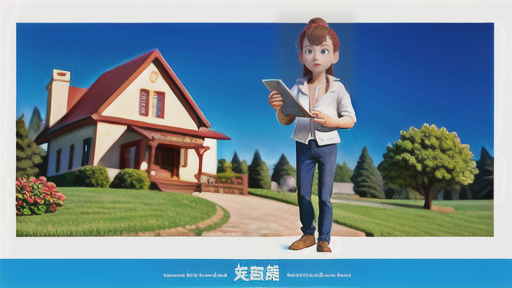
土地には、その利用方法によって様々な種類があります。今回取り上げる貸家建付地もその一つで、所有者が自ら家を建て、それを人に貸して家賃収入を得るための土地のことを指します。似た言葉に貸宅地がありますが、これは更地の状態で借り手に貸し、借り手が自分の家を建てるための土地です。つまり、貸家建付地では家が既に建っているのに対し、貸宅地では土地だけが貸し出されるという大きな違いがあります。
また、自分の家が建っている土地は自用地と呼ばれます。こちらは、住む目的で所有している土地なので、人に貸すことはありません。このように、土地の使い道によって貸家建付地、貸宅地、自用地と区別されます。そして、この違いは、税金にも影響を与えます。
例えば、固定資産税と都市計画税を考えてみましょう。これらの税金は、土地や家屋を持っている人が毎年支払う必要があります。貸家建付地の場合、一定の条件を満たすと、これらの税金が軽減される場合があります。これは、賃貸住宅の供給を促進するための優遇措置です。一方、自用地も一定の条件下で軽減措置が受けられますが、貸宅地にはこのような軽減措置はありません。
さらに、相続が発生した場合に支払う相続税も、土地の種類によって評価額が変わってきます。貸家建付地は、更地である貸宅地や、居住用である自用地に比べて、相続税評価額が低くなる傾向があります。これは、貸家建付地には既に建物が建っており、更地に戻すための費用や手間がかかることなどが考慮されるためです。
このように、土地の種類によって税金の優遇措置や相続税評価額が異なるため、土地の利用目的をしっかりと理解し、それぞれの特性を踏まえた上で適切な選択をすることが大切です。
| 土地の種類 | 説明 | 固定資産税・都市計画税 | 相続税評価額 |
|---|---|---|---|
| 貸家建付地 | 所有者が家を建て、それを人に貸して家賃収入を得るための土地 | 軽減措置あり(一定の条件を満たす場合) | 更地や自用地に比べて低い傾向 |
| 貸宅地 | 更地の状態で借り手に貸し、借り手が自分の家を建てるための土地 | 軽減措置なし | – |
| 自用地 | 住む目的で所有している土地 | 軽減措置あり(一定の条件を満たす場合) | – |
貸家建付地のメリット

貸家建付地を持つことには、様々な利点があります。中でも一番の利点は、毎月安定した家賃収入を得られることです。入居者から毎月きちんと家賃を受け取ることができれば、生活の基盤を安定させることができます。また、将来の年金生活の資金計画も安心して立てられます。老後の生活資金の不安を軽減できることは大きなメリットと言えるでしょう。
さらに、貸家建築のための費用や土地購入費用を借入金でまかなった場合、家賃収入を返済に充てることができます。家賃収入があることで、返済の負担を軽くし、計画的に借入金を減らしていくことが可能です。また、物価が全体的に上昇するインフレ局面においても、貸家建付地は有効な対策となります。一般的に物価が上昇すると、家賃もそれに合わせて上昇する傾向があります。そのため、現金や預貯金などの資産価値が目減りするリスクを軽減できます。家賃収入という形で安定した収入源を確保することで、インフレによる影響を和らげることができるのです。
加えて、税金面でのメリットも見逃せません。建物の価値は時間とともに下がっていくため、この減少分を減価償却費として計上できます。減価償却費を経費として計上することで、課税対象となる所得を減らし、節税効果を期待できます。つまり、貸家建付地を持つことは、収入の安定、インフレ対策、節税効果など、様々な側面から見て大きなメリットがあると言えるでしょう。
| メリット | 説明 |
|---|---|
| 安定した収入 | 毎月安定した家賃収入を得ることができ、生活基盤の安定や老後資金計画に役立ちます。 |
| 借入金の返済負担軽減 | 家賃収入を借入金の返済に充てることで、返済負担を軽減し、計画的な返済を可能にします。 |
| インフレ対策 | 物価上昇に伴い家賃も上昇する傾向があるため、現金や預貯金の資産価値目減りリスクを軽減できます。 |
| 節税効果 | 建物の減価償却費を経費として計上することで、課税対象となる所得を減らし、節税効果が期待できます。 |
貸家建付地のデメリット

貸家付きの土地には、確かに利益がある面もありますが、同時に注意すべき点もいくつかあります。まず一番に考えなければならないのは、借り手が見つからない可能性です。部屋が空いたままでは家賃収入はゼロとなり、計画していた利益が得られなくなるかもしれません。さらに、借り手が見つかった後でも、家賃を滞納されたり、借り手との間で問題が発生したりする可能性も常にあります。また建物は時間とともに老朽化するため、予想外の修理費用が発生することも念頭に置いておく必要があります。屋根の修理や水回りの交換など、大きな出費が必要になる場合もあります。
次に、地震や火災などの災害による被害を受ける可能性も忘れてはいけません。建物が損壊した場合、多額の修理費用が必要となるだけでなく、借り手が住めなくなることで家賃収入が途絶える可能性もあります。このような事態に備えて、適切な保険に加入しておくことが大切です。火災保険だけでなく、地震保険への加入も検討する必要があります。
さらに、貸家経営には手間と時間がかかることも認識しておく必要があります。建物の定期的な点検や清掃、修理の手配、借り手の募集や家賃の集金など、様々な作業が発生します。これらの作業を自分自身で行う場合は、かなりの時間と労力を費やすことになります。もし管理会社に委託する場合には、管理手数料などの費用が発生します。これらの費用も考慮に入れて、収益性をしっかりと見極める必要があります。このように、貸家付きの土地には様々なリスクが潜んでいるため、購入する前にはメリットだけでなくデメリットも十分に理解し、慎重に検討することが重要です。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 家賃収入 | 空室リスク(借り手が見つからない可能性) |
| 家賃滞納リスク | |
| 借り手とのトラブルリスク | |
| 建物の老朽化による修繕費用 | |
| 災害リスク(地震、火災など) | |
| 管理の手間と時間、または管理手数料 |
貸家建付地を持つ上での注意点

貸家建付地、つまり貸家を建てた土地を所有するということは、安定した収入を得られる一方、様々な責任やリスクを伴います。成功させるためには、事前の準備と計画、そして継続的な管理が欠かせません。まず第一に、賃貸経営に関する法律を理解することが重要です。賃貸借契約に関する法律や、建物の安全基準、更には税金に関する知識も必要です。法律を遵守しないことは、後々大きなトラブルに繋がる可能性があります。第二に、市場調査を入念に行いましょう。周辺の賃貸物件の状況、家賃相場、入居者層などを把握することで、適切な家賃設定や建物の設計ができます。需要の高い間取りや設備を取り入れることで、空室リスクを低減し、安定した経営を実現できます。第三に、建物の管理について検討しましょう。自分で管理を行うか、管理会社に委託するかを決め、それぞれのメリット、デメリットを比較検討します。管理会社に委託する場合には、信頼できる会社を選ぶことが重要です。費用だけでなく、対応の速さや丁寧さなども確認しましょう。第四に、リスク対策も重要です。空室による収入の減少や家賃滞納、地震や火災などの災害による損害など、様々なリスクが考えられます。これらのリスクに備えて、適切な保険に加入しておくことが大切です。最後に、長期的な視点を持つことも忘れてはなりません。建物の老朽化対策や設備の更新など、将来を見据えた計画と資金準備が必要です。賃貸経営は、入念な準備と継続的な努力によって、安定した収益と資産価値の維持を実現できるでしょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 賃貸経営に関する法律 | 賃貸借契約に関する法律、建物の安全基準、税金に関する知識など。法律を遵守しないと大きなトラブルになる可能性あり。 |
| 市場調査 | 周辺の賃貸物件の状況、家賃相場、入居者層などを把握。需要の高い間取りや設備を取り入れることで、空室リスクを低減。 |
| 建物の管理 | 自分で管理を行うか、管理会社に委託するかを決定。管理会社に委託する場合は、信頼できる会社を選ぶことが重要。費用だけでなく、対応の速さや丁寧さも確認。 |
| リスク対策 | 空室による収入の減少や家賃滞納、地震や火災などの災害による損害など、様々なリスクに備えて、適切な保険に加入。 |
| 長期的な視点 | 建物の老朽化対策や設備の更新など、将来を見据えた計画と資金準備。 |
まとめ

貸家は、土地を所有し、その上に建物を建てて人に貸し、毎月安定した家賃収入を得る方法です。家賃収入は、年金のような私的年金となり得るため、魅力的な資産運用方法として注目されています。しかし、良い面ばかりではありません。貸家経営には様々な課題も存在します。
まず、空室は大きな問題です。入居者が退去し、次の入居者が見つからない期間は、家賃収入が途絶えてしまいます。需要の少ない地域や、設備が老朽化した物件では、空室期間が長期化する恐れがあります。家賃収入を安定させるためには、空室対策が欠かせません。
次に、家賃滞納のリスクも無視できません。入居者が家賃を支払ってくれない場合、収入が減るだけでなく、督促の手間も発生します。滞納が長期化すると、法的措置が必要になる場合もあります。
さらに、建物の維持管理も重要な課題です。建物は経年劣化していくため、定期的な修繕やリフォームが必要です。屋根の修理や外壁の塗装、水回りの交換など、予想外の出費が発生することもあります。建物の維持管理を怠ると、入居者の募集に影響するだけでなく、建物の価値も低下してしまいます。
これらの課題を乗り越え、貸家経営を成功させるためには、事前の準備と計画が不可欠です。まず、市場調査を入念に行い、需要のある地域や物件の種類を把握する必要があります。適切な家賃設定も重要です。周辺の相場を参考に、高すぎず安すぎない家賃を設定することで、安定した入居者確保を目指します。信頼できる管理会社を選ぶことも大切です。管理会社に任せることで、入居者募集や家賃の管理、建物の維持管理など、様々な業務を効率的に行うことができます。また、火災保険や地震保険への加入など、リスク対策も忘れずに行いましょう。
加えて、貸家経営には、賃貸借契約に関する法律や税金の知識も必要です。専門家のアドバイスを受けながら、適切な対応を行うことが重要です。これらの要素を総合的に考慮し、長期的な視点で経営に取り組むことが、安定した家賃収入を確保し、資産価値を維持するための鍵となります。


